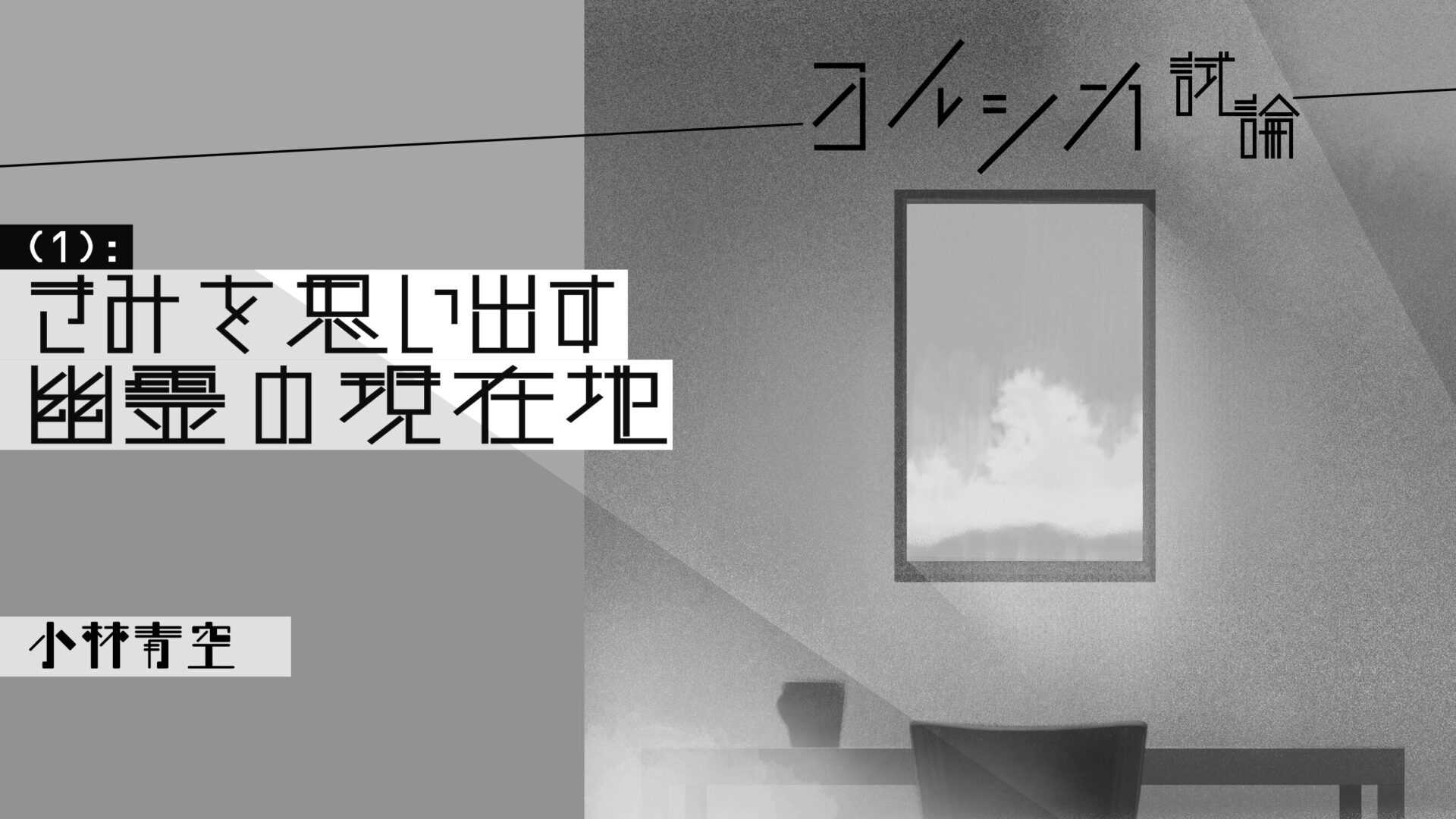白旗編集部の小林青空による『白旗 第2号 2023年秋』掲載の論考「ヨルシカ試論(1):きみを思い出す幽霊の現在地」を公開いたします。
0. 10月某日、机の前で
私は1人で机の前に座り、ヨルシカについての解釈を始めようとする。できれば私は、このバンドが作り出した音楽が含みもつ全ての可能性を書き切ってしまいたい。大それたことに、私はヨルシカの全てを、言葉にしてしまおうとしているのだ。
それはあまりに非倫理的なことであると私は思う。それに成功したとき、もしかしたらヨルシカの音楽に耳を傾ける必要がなくなってしまうのかもしれないから。ある批評家は、批評とは作品の壊死であると言った。その全てを論じきり、作品と共に爆発四散して、それにトドメを刺してしまうこと。そんなふうに私は簡単に割り切ることができない。反対に、良い批評は美味しいお酒と美味しい料理の組み合わせのように、相互を高め合うものだという人もいる。こちらの意見のほうに賛成したくはあるが、ただ心のどこかで、そんな都合のいい話はありえるのか、と私の中の他の私は問うている。
ただ、批評というものはみな、初めからなにか敗北を運命付けられて いるのかもしれない。少なくとも私は解釈を行える自信など持ち合わせてはいないのだし、言葉はいつも現実を掠め、ギリギリのところで対象を離れ去ってゆく感覚がする。批評はいつも、経験の全てに解釈を与えることを夢見ている。だが解釈行為は果てなく、現実を全て手中に収めることなど決してできようはずもない。よしんば解釈に成功した気がしても、私も解釈の対象も、もはやそれをなぜ望んでいたのかということについては、ほとんど忘れかけているのだ。 そもそも言葉なんていうものを知ってしまったから、私は現実を、他者を、その全てを知りたいと思ってしまったのだ。それが他者と繋がる唯一の回路であるし、それを言葉にすることが自分の輪郭をはっきりとさせるただひとつのやりかたであると、私はずっと信じてきてしまった。それはエゴイスティックな欲望だし、それは必ず失敗することを、よく了解しているにもかかわらずだ。そんな愚かな自分の姿に気がつくとき、ふと小さくて巨大な暗い穴が心の中に開くのを、私は感じる。
私の小さな机の前に空いた窓からは⻘々とした山並みが見える。大きな雲が遠く、山の後ろにそびえている。その光景を見るたび、この美しさをそっくりそのままあなたに伝えられたら、それだけで私はもう少し生き延びられると感じる。
しかし言葉を重ねれば重ねるほど、私はそれが全く馬鹿げた欲望であることに気づかざるを得ない。風景の全てを説明する言葉など、初めからどこにも存在しようがないからだ。私の言葉など、あらかじめあなたに届きはしない。もはや何かの拍子に、何かの間違いで届いてしまうことなど夢見たくもない。あなたにこの言葉が届く可能性が寸毫でも許されるなら、私はこの夢から解放されることなどないからだ。
遠く、ガラスの向こうの山を見続け、苦しむ。そんな瞬間に私はふと透明になってゆくのを感じる。それはこんなにも辛い現実から逃れるためなのか、私が自意識過剰になりすぎたためなのか。でも、消えない辛さの中で、私はふと長年感じたことのない安息を感じる。私にとって、ヨルシカはそういった感触に寄り添ってくれるバンドだ。私はこれを解釈しようと躍起になっているのだ。とはいえさすがに感傷的になりすぎた。忘れてくれてよい。
ただこれは、いつかのあなたに読まれるための手紙である。
1. 負け犬のアイロニー
私がこの文章を書くにあたり明確なモチベーションの一つとしているのは、ヨルシカの表現について語る文章があまり見当たらないことだ。正確に言えば彼らのファンダムの間では盛んに(主にその歌詞について)議論が行われれているのだが、熱心なリスナー以外が表現の内実に触れる機会は、おそらくなかなかない。
初めから頼りない直感的な主張をするが、どうやらヨルシカの音楽には独特の語りにくさのようなものがあり、それゆえポップスをめぐる言説の権威と価値のポリティクスにおいては、ほとんど敗者の立場に甘んじていると言ってみることを許してほしい。端的に言えばヨルシカは「エラく」ないとされているような気がする。危うい観測結果であることを承知の上で、私の友人数人の感想を総合すれば、その理由は「音楽的な表現としての技法や歌詞の世界観が、既存のポップスや文芸の反復や変奏に思える」といったところなんじゃないだろうかと思う。例えばヨルシカ(やn-buna)のメロディやアレンジを語ろうとするとき、2010年代の邦ロック/ボカロという二項対立が持ち出されることがある1。このような語りには一定の説得力があることは理解するが、議論はしぜん「ボカロっぽさ」「邦ロックっぽさ」といった、どうも語りにくい特徴量をめぐる微妙な方向になりがちだ。このことはヨルシカの音楽的な発明についての語りにくさを、ある意味逆説的に示しているようにも思える。
また歌詞という点から言っても、ヨルシカの歌詞が反復するいくつかの言葉やモチーフたち──夏、打ち捨てられたバス停、花火、前世──は、我々に2000年代前後に数多く生み出された恋愛ゲームが働かせてきたような想像力(ありていに言ってしまおう、「セカイ系想像力」)の範疇内に納めて語ってしまいたくなるものが多い。実際ヨルシカが初期から持っていた歌詞の基本的デザイン、つまり「私」と「君」の運命的・閉鎖的な関係の強調は、メジャー2ndアルバム『エルマ』にかけてのグランドストーリーの強力な通奏低音となる。「セカイ系」とヨルシカ、というテーマも誘惑的で、同時にユニークに語りにくい。このように「なぜヨルシカか」という問いは、それなりの答えづらさを持った問いだ。
とはいえ、「私」と「君」の運命的・閉鎖的な関係の強調」という要素は、ヨルシカのことを考えてゆくときにどうにも避けて考えにくい。『夏草が邪魔をする』(2017)『負け犬にアンコールはいらない』(2018)『だから僕は音楽を辞めた』(2019)『エルマ』(2019)という明らかな四連作は、「私」と「君」、つまり自己と大文字の他者のコミュニケーションという倫理的な主題に、どこまでも直接的である。先に書いてしまえば、この古典的なテーマに対する直接さ・脇目もふらぬ真面目さにこそ、私はまずヨルシカの表現の特異さを見出す。その程度が強ければ強いほど、ほとんど必然的に「私」のアイロニカルな自己否定の表明が招来される。こうした構図は『負け犬にアンコールはいらない』『だから僕は音楽を辞めた』収録曲に顕著だ。まずはこの二つのアルバムの収録曲を聴きながら、ヨルシカ流アイロニーの濃淡を読み取ってゆく。
さて、最初の分析をどの曲から始めるべきだろうか。わからないままに、とりあえずYouTube上での再生数が多い曲を対象としてみる。もっとも再生数の多い曲といえば、〈ただ君に晴れ〉(『負け犬にアンコールはいらない』収録)だ。この曲の歌詞が言わんとすること、取っている態度を、まずは丁寧に洗い出してみよう。
夜に浮かんでいた
〈ただ君に晴れ〉(作詞・作曲:n-buna)
海月のような月が爆ぜた
バス停の背を覗けば
あの夏の君が頭にいる
だけ
「夜に浮かんでいた海月のような月が爆ぜた」とは、おそらく水面に投影されている月の像が、水面に対するなんらかの衝撃に合わせて揺動する様子を指す。私が夜、水面をただ見つめているイメージがここで提示されるのだが、その私はすぐに「バス停の背を覗く」私へと変化してゆく。はたして、その私の内面で巻き起こっているのは「あの夏の君が頭にいる」という事態である。
この私の立っている地点の急激な入れ替わりは、しかしその傍観者的な態度によって一貫している。私がどうにも干渉のしようのない場所で「海月のような月が爆ぜ」るのであり、「あの夏の君が頭にいる」のである(後者について「あの夏の君を思い出す」という能動的な表現が周到に避けられていることには注目しておきたい)。つまり、水面に映った月と、私の頭の中にだけ存在する君の像は明らかに重ね合わせられており、また水面に映った月がすでに破裂してしまった、というはじめに提出されるイメージは、「私の頭の中の君」の存在はすでに危ういものであることを示唆している。この危うさは「あの夏の君」の存在の根拠が、あくまで「頭にいる」ことにしか求められないことを強調するような、水面の月を揺らすような、「だけ」の特殊な譜割によっても確かめられる。この冒頭の二文が伝えんとしているイメージは、その見かけの清澄さとは裏腹に、すでに「君」の存在の確からしさをめぐる不安を示している。
このように、この曲の歌詞は冒頭から「僕」の「君」に対する心理的疎隔を問題としている。このとき、「僕」と「君」の距離は圧倒的に埋めがたいものとして描かれる。一番サビの歌詞を見てみよう。
追いつけないまま大人になって
〈ただ君に晴れ〉
君のポケットに夜が咲く
口に出せないなら僕は一人だ
それでいいからもう諦めてる
君は私をおいて大人になってしまった2。「君のポケットに夜が咲く」とは婉曲的な表現だが、「君」がすでに「僕」の知らない夜の領域にタッチしてしまったことを示すのだと読める。そうした「君」に対して私はなにかそれを引き止めるような未練の言葉を「口に出せない」。「僕」のとりうべき態度は「それでいい」と「諦める」ことになる。
表層的に考えるならある種の一方的なイノセントな恋心の喪失を書いているように読める。しかしながら、失恋のことを書くにしては、事態に対する捉えかたはあまりに抽象的であるし、あまりに独善的であるように見える。そう、ここには徹底的に「僕」の無能感しか存在しない。私はあなたを引き止める言葉を発することさえできず、それを試みることすらせずに諦めるのである。「僕」と「君」の心理的な距離は一方的に「僕」の側より主張され、「僕」はその距離を能動的に縮めることを試みることさえしていないように見える。したがって、「僕」と「君」の距離は、歌詞の中の「僕」にとっても、まったくサイコロジカルな問題として理解されることになる。ここでヨルシカの歌詞の中で数多く登場する、非常に重要な問題が立ち現れてくる。「記憶」「思い出」の問題である。
夏日乾いた雲山桜桃海錆びた標識
記憶の中はいつも夏の匂いがする
写真なんて紙切れだ思い出なんてただの塵だ
それがわからないから、口をつぐんだまま絶えず君のいこふ記憶に夏の野石一つ
〈ただ君に晴れ〉
「夏日」「乾いた雲」といった表現は、まず現実とは離れたなにか美しい夏の場所を定義する。そこには匂いがあり、手触りがあり、この場所とこの時間にしかありえないなにがしかの質感を持っている。「じきに夏が暮れても/きっときっと覚えてるから」という歌詞からも、このかけがえのない質感を持った夏の記憶というものが、「君」にまつわる記憶、あのとき「君」の存在の確からしさをいくらか保証するものであるようだ。しかしながらそうした記憶を視覚表象として焼き付けておくかにみえる「写真」は紙切れであり、「思い出」はただの塵であると、語り手の「僕」は吐き捨てる。こうしたことをどこかでまだ信じられていないことが、彼が口をつぐんでしまい、言葉によって他者にタッチしようとすらしなくなった原因であるようだ。こうした彼の孤独な有様は、正岡子規の句を引用しながら、「絶えず君のいこふ~」以下に綴られる。君が絶えず存在する記憶の感触だけを語り手は弄んでおり、そこには「夏の野石」がごろんと横たわっている。音を欠いた静物的なイメージは、このイメージの中の「君」と語り手の間にあるどこまでも深い溝を想起させる。
「僕」が「君」にアクセスすることができるのは、記憶や思い出の中だけであるのであり、その存在の儚さに気づきつつもどうしても「思い出」を手のひらの上で弄びつづけてしまう自閉的な語り手が、ここには描き出されている。「君」と会話をしようと試みないのはこの美しい「記憶」「思い出」が傷ついてしまうことを恐れてのことであると、ひとまずは考えられる。事実、この歌詞の最後はこのように締めくくられる。
口に出せなくても僕ら一つだ
〈ただ君に晴れ〉
それでいいだろう、もう
君の思い出を噛み締めてる
だけ
最終的に言葉による君とのコミュニケーションを断念し、「僕ら一つ」であることを語り手は主張するが、その主張は明確に投げやりなものとなっている。「君の思い出を噛み締めてるだけ」と主張する語り手の態度には、すでに自嘲的なニュアンスがにじんでいる。「君」に対するなんらの働きかけをしようともしないまま、ただ「君に晴れ」があることを祈り、思い出を「噛みしめる」ばかりである自分に対するアイロニーを表明し、この曲は終わっていく。
君とのコミュニケーションが決定的に失敗することを知っている語り手にとって、「君」に対する倫理的な態度は厳しく制限される。〈ただ君に晴れ〉ではもはや今日の気候が「晴れ」であることを望む、というところまで、君に対する働きかけは抽象化されねばならなかった。では何ができるのか。もちろんこうした人間にとっては、詩を読み、歌を作ることしかできないのであろう。〈負け犬にアンコールはいらない〉はこのように終わる。
もういい、もうこんな人生全部をかけたい
〈負け犬にアンコールはいらない〉(作詞・作曲:n-buna)
負け犬なりに後悔ばっか歌って
また夢に負けて昨日をいとおしんで
「君」の記憶や思い出にとらわれる「こんな人生」はここにおいて「全部かけ」られる。過去の後悔ばかりを歌うこと、「負け犬が吠えるように生きて」ゆくことが、決然として歌われる。「君」への絶望的な届かなさ、なにかの喪失の感覚といったマイナスの要素はすべて反転し、世界への働きかけへと変わってゆく。
事実、「負け犬が吠えるように」詩を書き、歌を作ることは、「君」との自閉的な思い出の場に閉じこもることしかできなかった語り手にとって、パーソナルな領域における小さな復興というよりむしろ、「私」を一気に世界に向けて解き放つダイナミックな運動である。語り手は「世界平和」や「愛」といったおためごかしを唱える「偽善者」に「吠え面かけよ」と凄み、そこにはたしかに「私」の領域が形作られてゆくのだ。ここでドラマチックに語り手が語りきったものは、アイロニーが新たな自我を世界に対して構築してゆく、その過程である。いわばこの曲で歌った決意表明の実践として、先に論じた〈ただ君に晴れ〉などの曲が存在することが、『負け犬にアンコールはいらない』というアルバムでは強く示されているように思われる。
しかしながら、続くアルバム『だから僕は音楽を辞めた』の表題曲〈だから僕は音楽を辞めた〉では、なぜか一転してそうした試みがすべて破棄される。
考えたってわからないし
〈だから僕は音楽を辞めた〉(作詞・作曲:n-buna)
青空の下、君を待った
風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像
ねえ、これからどうなるんだろうね
進め方教わらないんだよ
君の目を見た何も言えず僕は歩いた
「考えたってわからないし」という地点に、再び語り手は後退している。再び、彼は「⻘空の下」で「君」を待つのであり、こうした閉塞した心理状態を「抜け出す想像」しかできなくなる。「君の目」を見れどそこに言葉はなく、「何も言えず」ただ歩く「僕」の姿のみが描かれる。
君を思い出すほかないこと、頭の中にしか君はいないこと、君に話しかけることができないこと──こうした「負け犬」としてのポジションをすべて反転させて、とにもかくにも「負け犬」としての私の位置をやぶれかぶれに主張してみる試みは、やはりなにがしかの袋小路にたどり着いてしまったようだ。「君」への届かなさをアイロニカルに世界に叩きつけることすらできなくなってしまった詩人に、もう何一つ「この私」を世界に向けて主張する際の寄る辺となるような地点の一つもあるわけがない。できることはただ一つ、自分をここまで追い詰めた世界に対する呪詛を撒き散らすことである。
間違ってるんだよ
〈だから僕は音楽を辞めた〉
わかってないよ、あんたら人間も
本当も愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ
正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ
考えたんだ あんたのせいだ
もはや「あんたら人間」に対して「間違ってるんだよ」とむやみな攻撃をしてみる語り手しか残ってはいない。この世の一切合切がもうどうでもいいのだが、こうした自暴自棄の瞬間にすら、世界を否定する自我さえも「自我」と呼ぶには値しないかもしれないことを、正しいことを知りたがることも「防衛本能」にすぎないと表現する語り手は強く認識してしまう。悲劇は、ここにおいてすらままならぬ自分の感情を「防衛本能」だと考えてしまうことである。こんな怪しげな言葉を使ってしまったことにより、ままならぬ感情は決して外部化されることなく、神秘のヴェールだけを剥がされて自分の中に秘められてゆくのだから。ゆえに「君」をめぐって思い悩む自分を「負け犬」と呼ぶほどに自罰的であった語り手は、その自罰の強さだけ「あんた」を憎むしかない。ポイントは「あんた」とは誰か、どこにも明示がされないところにある。おそらく「あんた」は誰でもない。「あんた」はただ、「負け犬」でさえ既にあれなくなってしまった私が、自分を憎むことすらできなくなってしまったこの私が、憎しみをぶつけるために仮構された「なにか」なのだろう。
この曲の最後で語り手は少しだけ冷静になる。「僕だって信念があった」。その信念は「僕」を「僕」たらしめるものだったが「今じゃ塵みたいな想いだ」と吐き捨てる。「何度でも君を書いた」とあるとおり、語り手にとっては音楽を作ることがすなわち、君を書くことだった。そうした試みがすべて破裂した。「だから僕は音楽を辞めた」。
「君」への不通という事態を、逆に世界中に公開してみようとする肥大したエゴの飛翔の試みは、ここにおいてあっけなく墜落しようとしている。墜落してゆく自分を追認し、それを美的に描くことすら、語り手は放棄してしまっている。事実ヨルシカがある程度明確に提示しているアルバム内のストーリーラインによれば、この曲を残して語り手は自殺してしまうのだ。ただし、この曲で主張されることの行間の広さに、どうして「僕」は音楽を辞めてしまったのか、そのことの消息を追いかけることを聴き手に要求してやまないところに、墜落したエゴの最後の瞬きをみてもよい。
ここにとりあげたのはヨルシカの押しも押されぬ代表曲ばかりだ。いずれも代表曲であるだけに、これらをつなげて考えれば、ヨルシカの主な語り手がたどったアイロニーと自己否定の成長の過程が滑らかに示される。ただ一方で、ヨルシカが自らを据え置く現在地点、こうした自己意識の隘路は世界中の詩人や小説家が幾度となく描いてきた風景であるし、ヨルシカの語り手はこうした景色をなぞる凡庸な「私」をことさらに切実に演出するきらいがあると言われれば、ある程度その通りと答えるしかないとも感ずる。
しかしながら、繰り返すが、私はヨルシカの美点はこうした自己意識の問題をほぼ全ての曲でしつこく取り扱い続け、取っ組み合い続けたところにあると考えている。加えて、こうした問題は、これまでみてきたように、全く「私」の中の心理的な劇場で展開される。「君」との不通はどこまでも前提され、他者はいつも記憶や思い出の中にある他者の影であると言ってよい。すべてが「私」の抽象的で心理的な宇宙へと回収されてしまうこと──そうした「極端に近代的な自我」の問題と呼ぶべきものこそ、ヨルシカが常に取り上げる主題である。
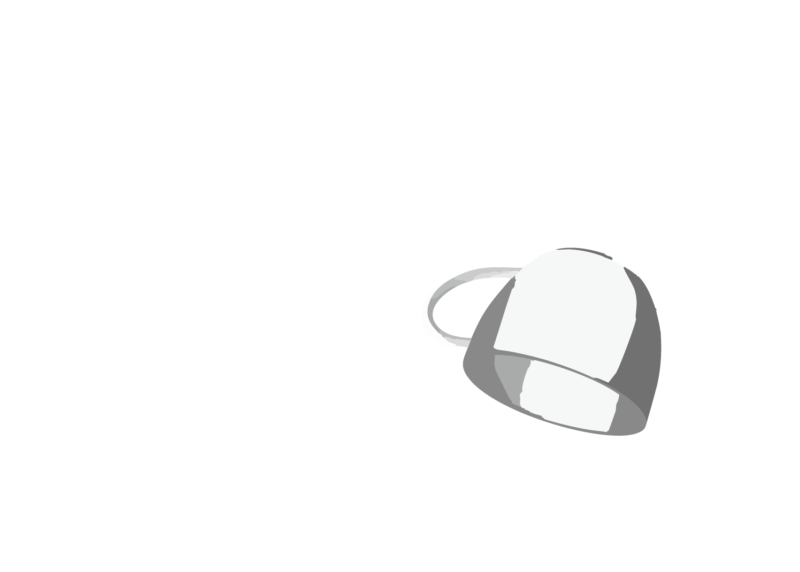
したがって、ヨルシカというバンドの曲が私の鼻先に突きつけてくるものは、徹底的に自己意識的で、なおかつ倫理的な問いだ。それは独善的でありながら、他者にどこまでも誠実であろうとする、あらかじめ破綻した試みである。ヨルシカの過剰なほどのシリアスなトーンは、私に以下のようなもの思いを引き起こさずにはおかない──自己意識の問題はいつだって凡庸かつ緊急だ。我々はそれを解く一般公式を、結局編み出すことができないままでいるんじゃないか。だからこそ、間違っていても、凡庸でも、徹底的に自分ひとりきりで悩むことが幾分か人倫にかなうことなのではないか。それについて適当なところで得心したり他人の真似をしたりして、ぼんやりと解くのを辞めてしまうやつらのほうがよっぽど凡庸ではないのか。
いずれにせよ自己意識との決死のとっくみあいを問題にするとき、大事に考えるべきなのはそのとっくみあいがどのような経過をたどるかということではなく、どのようにそれが表現されたかということにある。つまりヨルシカにおいては、なにゆえにこうした自閉的なアイロニーの隘路に語り手が迷い込まねばならなかったのか、ということをより問い立てる必要があるだろう。ここまでみてきたように、語り手は「君」とのコミュニケーションを完全に立たれた無能な「負け犬」として自分を定義しつつ、「負け犬」なりに「君」の表現を全世界に発信することを選び取ったが、どうやらそうした試みがあらかじめ内破していることに気づき、音楽を辞めてしまう。なぜそもそも語り手は「負け犬」として自分を認識することになってしまったのか。「負け犬」が「君」を詩にすることによってなにがしかを回復しようとする試みは、どの時点で間違っていたのか。そうしたことについて、いまだ考える必要がある。
・お知らせ
『白旗 第2号』は現在全国の店舗で好評発売中です。一部書店はネット通販にも対応しています。
脚注
- https://realsound.jp/2020/09/post-613823.htmlなど。
- 「君」の成熟のスピードに置いていかれてしまった「僕」が「君」を一方的にまなざす、という構図から、この歌詞においてすでに「幽霊」の影を読み取ることもできる。